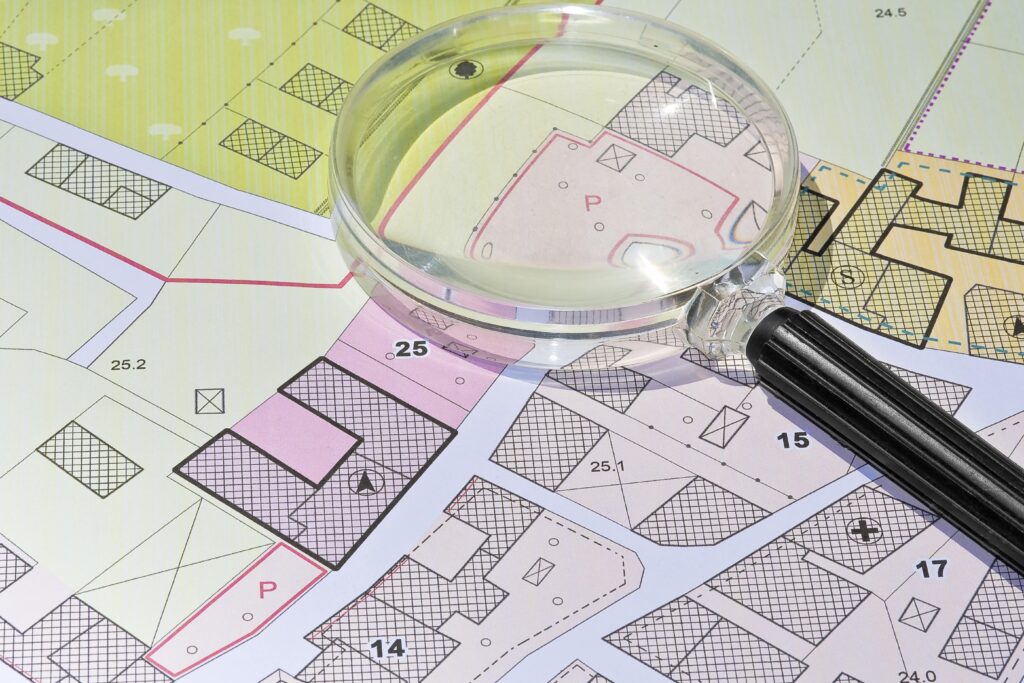CADオペレーターが在宅勤務を実現するにはどうすればいい?
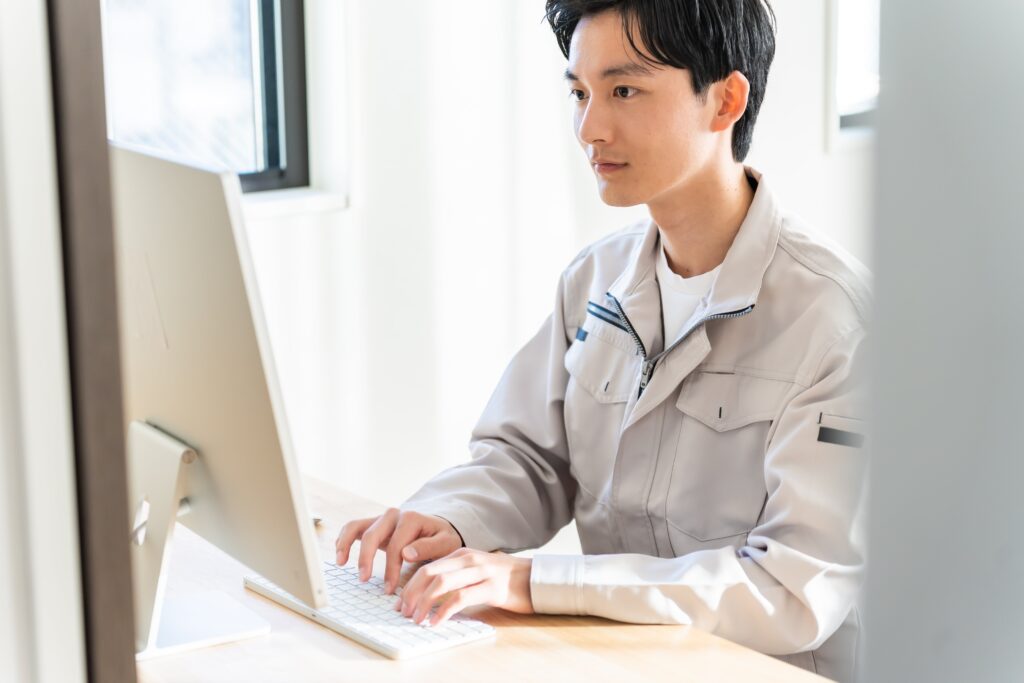
CADオペレーターは在宅勤務が可能な業種ですが、実際にはほとんどのCADオペレーターは出社して業務を行っています。本記事では、CADオペレーターの在宅勤務が難しいとされる理由と、在宅勤務を実現させるにはどうすればいいのかを深掘りして解説します。柔軟な働き方を目指しているCADオペレーターの人は、ぜひご一読ください。
CADオペレーターの在宅勤務が難しいとされる理由
建設業界において、CADオペレーターの働き方は近年注目されているテーマの一つです。特にコロナ禍以降、多くの業種でリモートワークが進んだことから「CADオペレーターも在宅勤務ができるのではないか」と考える人も増えています。
しかし、実際には多くのCADオペレーターが現場や事務所に出社して働かざるを得ない状況が続いています。その理由は、大きく分けて以下の3つです。
施工管理とのコミュニケーションの問題
まず第一の理由は、施工管理とのコミュニケーションの問題です。CADオペレーターは、現場の施工管理が担うべき業務の一部を代わりに担う存在です。そのため、施工管理とのやり取りは頻繁に発生します。
現場であれば、施工管理者がその場で直接説明したり指示を出したりできるため、円滑にコミュニケーションが進みやすいです。しかし、在宅勤務の場合はチャットや電話などのツールを介する必要があり、連絡や指示に余分な時間と労力がかかります。
とくに図面の修正や詳細な説明が必要な場面では、口頭や現場での身振りを交えた説明の方が伝達効率は格段に高いため、遠隔での対応は非効率になりがちです。その結果、施工管理側から見れば、CADオペレーターが在宅勤務をするメリットは薄く、むしろデメリットの方が目立ってしまいます。
業務がCADのみに留まらない
次に、CADオペレーターの仕事がCAD業務だけに留まらないという点があります。現場の実情として、CADオペレーターは図面の作成や修正以外にも多くの雑務を担っています。
例えば、施工管理が現場に出ている間の電話対応や、工事に関する各種安全書類・報告書の作成、さらには事務所内でのゴミ袋の交換や荷物の受け取りといった業務まで任されることも珍しくありません。
施工管理は外での業務が中心となるため、事務所に常駐する人が誰もいない状況が頻繁に発生します。その際にCADオペレーターが事務所にいてくれると、現場を円滑に進めるうえで非常に助かる存在となります。
さらに、新築工事においては、作業の時期によってCAD業務の量が変動しやすいです。躯体工事の段階では施工図の作成、内装工事の段階では竣工図の作成といった多くの役割があります。
しかし、竣工図を完成させてしまうとCAD業務は大幅に減ります。そうなると残る仕事はCAD以外の雑務である場合も多く、事務所に常駐している方が施工管理にとって都合が良いのです。
育成の観点
三つ目の理由は教育・育成の観点です。経験豊富で自立的に業務を進められるCADオペレーターであれば、在宅勤務でも問題は少ないでしょう。しかし、多くのCADオペレーターはキャリアの途上にあり、施工管理からの指導やアドバイスを必要としています。
とくに初心者や経験の浅いオペレーターの場合、作業手順や図面の意図を理解するために細かい説明や確認が欠かせません。教育を行う施工管理からすれば、同じ空間にいて直接指導できる方がはるかに効率的であり、在宅勤務ではどうしても教えにくくなってしまいます。
リモート環境では図面データの共有は可能であっても、実際の指導や質問対応のスピード感には限界があり、育成には不向きなのが現状です。
CADオペレーターが在宅勤務を実現させる方法
上記の通り、多くのCADオペレーターは出社勤務を余儀なくされています。その一方で、一定の条件を満たせば在宅勤務を実現することも不可能ではありません。ここでは、CADオペレーターが在宅勤務を叶えるための条件や具体的な方法について整理します。
高い実力を身に着ける
まず大前提として、CADオペレーターが在宅勤務を実現するには「高い実力」が不可欠です。経験が浅く、施工管理からの教育や指導を必要とする段階では、リモート環境は大きなハードルとなります。在宅勤務の場合、指導や質問への対応がオンライン経由となり、コミュニケーションコストが増加します。
そのため、施工管理側から見れば、教育が必要な人材をわざわざ在宅で働かせるメリットはありません。むしろ「現場にいてくれる人」を優先的に採用するのが一般的です。したがって、在宅勤務を希望するのであれば「この人でなければならない」と思わせるほどのスキルを身につける必要があります。
具体的には、施工管理に対して必要な業務を主体的に提案できる能力や、図面の正確な読み書きスキル、建築や設備に関する図記号や専門工事への理解が求められます。さらに、AutoCAD、CADWe’ll Tfas、Rebro、Revit、RevitMEPなど主要なCADソフトを扱える技術も必須です。
そのうえで、勤務先の会社特有のフォーマットや業務の進め方を理解していること、そして実務経験が豊富であることが、在宅勤務の実現を後押しする要素となります。これらのスキルを兼ね備えて初めて、施工管理や会社側から信頼を得られ、在宅勤務を許容されやすくなるのです。
現場の規模・種類を考慮する
次に、働く現場の規模や種類も大きく影響します。小規模現場ではCAD業務以外にも電話対応や書類作成、雑務など幅広い業務をCADオペレーターに任せるケースが多く、在宅勤務は難しいのが現状です。しかし、大型現場の場合は状況が異なります。
工事規模が大きい分、施工図や竣工図などの図面業務が大量に発生するため、CAD業務だけで人材を専任で配置する必要が出てきます。
このような現場ではCADオペレーターの専門性が強く求められるため、在宅勤務でも業務を進められる体制が整いやすいのです。したがって、在宅勤務を望むのであれば、できる限り大型現場で働くチャンスを探すことが重要になります。
また、勤務先として「支店」や「営業所」を選ぶことも有効な方法です。大手建設会社の支店や営業所には、現場を後方支援する「サポートチーム」が存在し、各現場から依頼される業務を一括で引き受ける仕組みがあります。
このような組織では、CAD業務のみを担うオペレーターを専任で雇うケースも多く、CADに集中できる環境が整っています。
加えて、支店業務は現場との物理的な距離があるため、CADオペレーターの在宅勤務が比較的導入しやすいです。実力と信頼を積み重ねれば、支店勤務を通じて在宅ワークを実現できる可能性が高まります。
さらに、勤務地を都市部に絞ることも重要なポイントです。東京や大阪、福岡といった大都市圏には、多数の建設会社や現場が集まっており、それに比例してCADオペレーターの需要も高まります。
需要が多ければ、在宅勤務という条件を受け入れる企業も現れやすくなります。加えて、都市部には大型現場が集中しているため、前述の「CAD専任業務」に携わるチャンスも増えやすいです。地方に比べ、都会での就業は在宅勤務の可能性を高める要因となるのです。
入社時に交渉する
最後に、入社の段階で在宅勤務を交渉するという方法があります。通常、出社が前提の中で入社後に「在宅勤務を希望したい」と申し出ても、施工管理側からは抵抗を受ける場合が多いでしょう。
しかし、最初から在宅勤務を条件に雇用契約を結ぶのであれば、企業側も承知のうえで採用するため、後から摩擦が生じにくくなります。もちろん、その分採用のハードルは高くなりますが、一度契約を結べば在宅勤務を安定的に続けられる可能性は大きく高まります。
まとめ
CADオペレーターの在宅勤務は、一見可能に思えるものの、施工管理との密な連携や雑務対応、教育面での課題があり、現実には出社勤務が主流となっています。しかし、経験やスキルを積み重ね、施工管理から「この人でなければ」と評価されるレベルに達すれば、在宅勤務の実現は十分に可能です。とくに、大型現場や支店・営業所、さらに都市部での勤務ではCAD業務に専念できる環境が整いやすく、リモートワークの可能性も広がります。加えて、入社時から在宅勤務を前提に条件交渉を行うことで、後の摩擦を避けつつ理想の働き方を得られるチャンスも生まれます。柔軟な働き方を目指すのであれば、自身のスキルアップと戦略的な環境選びがカギとなるでしょう。