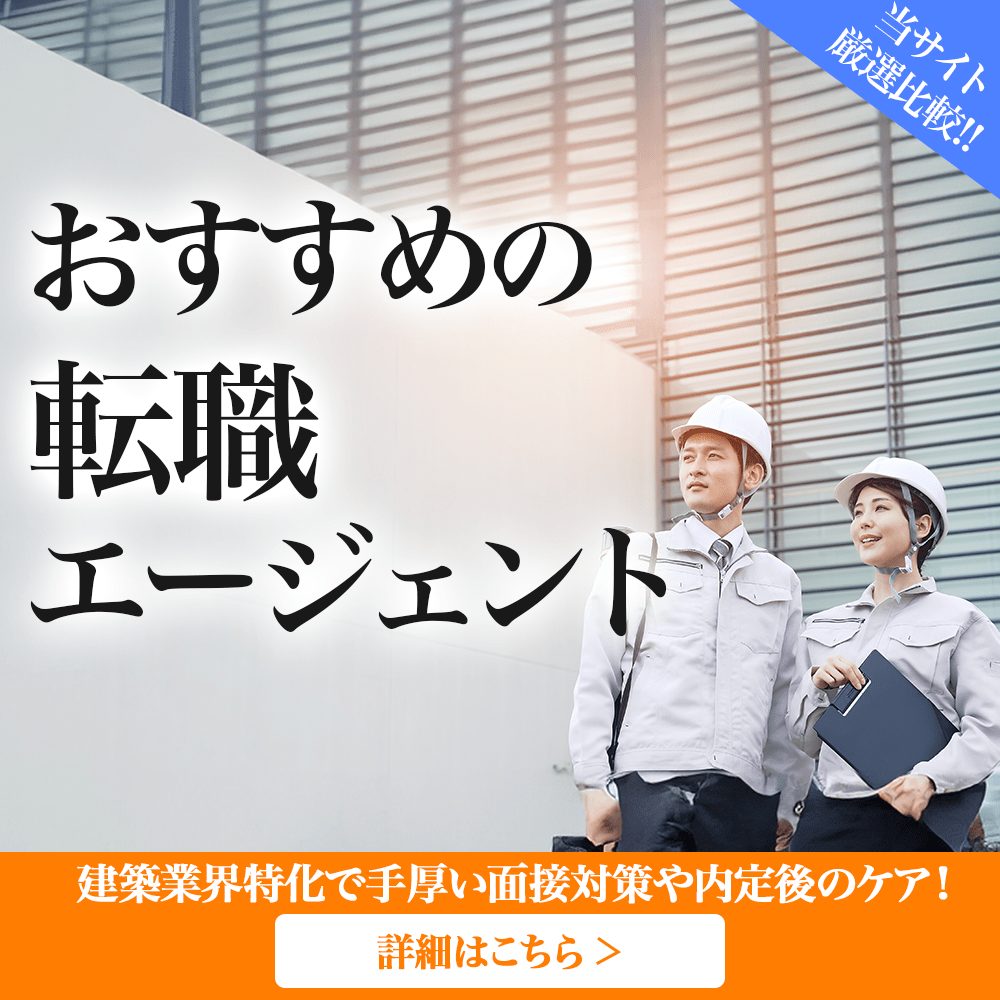建築設計業界で働くなら運転免許証は必須?免許がなくてもできる仕事はある?
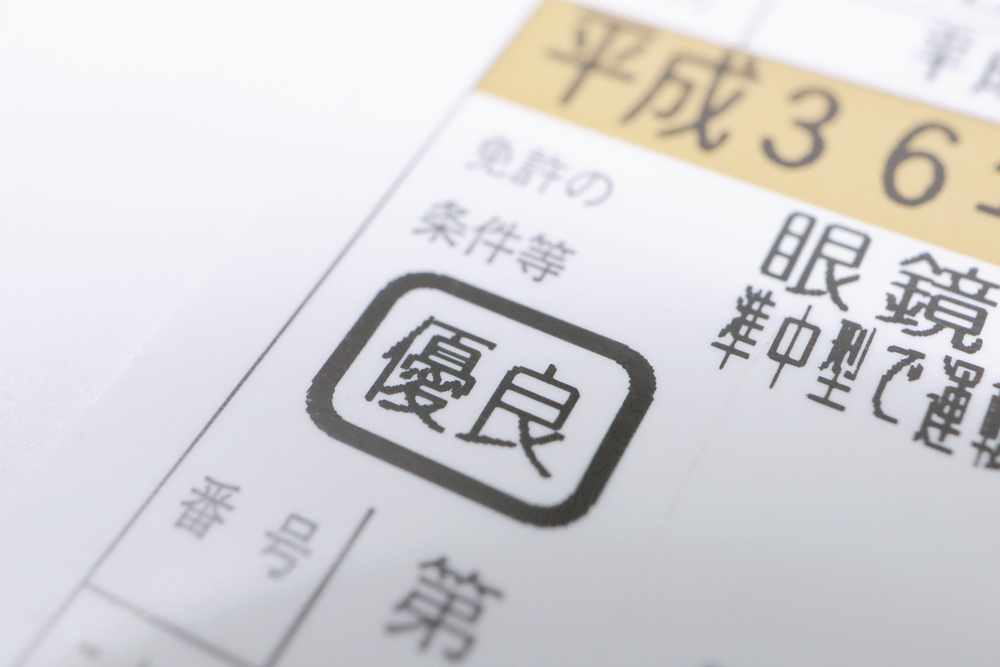
これから建設設計業界で働きたいと考えている人に、今回の記事はおすすめです。例外として、経理や事務に従事している人や、派遣社員で製図のみの仕事をしている人であれば運転免許は必須ではありません。しかし、それ以外の人は必須といえるでしょう。ただ免許を持っているだけでは採用されない場合もあるので注意が必要です。
建築業界で働くなら車の運転免許は必須?
都心部で職場と現場が駅から近い場合であれば問題ありませんが、郊外や田舎では必須の資格といえるでしょう。
運転免許は必須といえる
自宅から職場までの移動は、徒歩または公共交通機関を利用するので運転免許を持っていなくても問題ないと考えている人は注意が必要です。たとえ通勤で車を運転しなくても仕事で運転することが考えられるからです。この際、ペーパードライバーでも問題ないわけではありません。免許を持っていることが必要なわけではなく、車を運転できなければ意味がないからです。
運転免許が必要な理由
現場まで移動するときに車を運転することになります。都心部に物件があれば、駅から徒歩数分ということも珍しくないため、車で現場に向かうよりもコストも時間もかからないことがありますが、郊外や田舎の場合はそのようにいかないでしょう。電車やバスの本数が限られているだけではなく、電車やバスが走行していないことも考えられます。移動のたびにタクシーとなると、1日に複数の現場を見て回るときにコストがかかってしまいます。毎回そのようなことを行っているとスムーズに移動できません。
また、職場から現場に向かうだけではなく、市役所まで書類を提出することや、ホームセンターなどで資材を購入することも求められているので、車の運転免許は必須といえます。この際、AT限定であっても車の運転免許を持っていることが大事です。企業にもよりますが、運転免許を取得していない人を採用しない場合もあります。
例外もある
建設業界で勤務するすべての人が車の運転免許を取得しなければいけないわけではありません。例外として、派遣社員で製図のみの仕事をしていて現場に足を運ぶことがない人や、事務や経理の仕事に従事している人は必須ではありません。そのため、こちらの業務に従事している人の求人欄には運転免許の有無は求められていないことがほとんどです。ただし、それ以外の業務に従事している人は、現場や役所などに移動することが多くなるので、車の運転免許を持っていることが求められます。
MT車も運転できる運転免許を取得したほうがいい?
AT車のみ運転できるよりもMT車も運転できたほうが好ましいのは事実です。社用車がMT車であることも珍しくありません。就業後に車の運転でストレスを感じないように準備しておきましょう。
MT免許の必要性
一般的な車ではAT車が普及しているので、MT車を運転する機会が減少している人も少なくないでしょう。職場から現場までの移動や市役所などに書類を提出する場合であればAT車でも問題ありませんが、トラックなどを操縦するときはMT車の場合がほとんどです。そのようなことから社用車がMT車であることも珍しくありません。車の運転免許を持っているけれどMT車の運転が苦手な人やAT限定免許しか持っていない人は現場で苦労することが予想されます。
また、職人や大工ではないので、トラックを移動させる機会はほとんどありませんが、急にトラックを移動するように求められたときに近くに職人や大工がいなければ対応しなければいけません。身近にトラックがある現場で働く人として必要な免許といえるでしょう。
限定解除の方法
就職後に限定解除を行うと時間がかかるので、就職前に行うようにします。限定解除の方法は、自動車教習所で数回講習を受講し、その後に技能試験に合格しなければいけません。講習の回数は1~数回と違いがあり、早ければ1日で講習は終了します。
しかし、技能試験は毎日行われているわけではなく、決められた日に受験しなければいけないので勤務日と重複してしまうことが考えられます。また、技能試験に合格して限定解除ができた場合でも、しばらくの間は運転に慣れる必要があるので、業務に従事しながら限定解除を行うのは負担が大きいといえるでしょう。
法改正により運転できない車両があるので注意が必要
中型の自動車は普通自動車運転免許で運転できなくなっています。平成29年3月以前に運転免許を取得した人は注意しましょう。これまでとは異なり、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の車であれば運転できるようになっています。
準中型免許の取得を目指す方法もある
車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗車定員10人以下の車は、準中型免許を取得することで運転できます。トラックだけではなく、ミキサー車、ユニックなども運転できるので仕事の幅が広がります。準中型免許を取得するときに発生する費用は会社が負担することがほとんどなので、希望する人は相談しましょう。
ペーパードライバーでも免許・資格欄に記入してOK
運転免許を取得していることは事実なので記入しても問題ありません。ただし、ペーパードライバー不可の求人もあるので、そのような場合は自分の運転技術を高めてから応募するようにしましょう。
免許・資格欄に記入できる
運転免許を取得していることは事実なので、記入しても問題ありません。ただし、仕事で車の運転が必須であれば就業するまでに車の運転に慣れておく必要があります。採用する企業は、車の運転免許を取得していることに関心があるわけではなく、車の運転を問題なくできることに関心があるからです。運転にブランクがあり自信がない人は、自動車教習所などが行っているペーパードライバー講習に参加するなどして不安を解消しておきましょう。
運転にブランクがあることは面接のときに伝える
ペーパードライバーであることは恥ずかしくありません。面接のときには打ち明けておいたほうがよい場合もあります。不安がある人は、業務でどの程度の運転技術が求められているのか確認しましょう。たとえば、現場に向かうときだけ車の運転を行うのであれば、トラックなどを運転する必要がありません。また、社用車がAT車で、採用担当者からMT車を運転する機会がないと伝えられれば、AT車の運転に慣れるだけで問題ないでしょう。このようにして不安を解消しておくことが必要です。
ペーパードライバー不可の求人もある
企業にもよりますが、ペーパードライバー不可の場合もあります。この場合は応募を諦めてほかの企業の求人を探す方法と、ペーパードライバーを克服して応募する方法の2つがあります。どうしてもその企業で就業したい場合は、採用担当者にいつまでに運転ができるようになれば問題ないのか確認する方法もあります。それまでにペーパードライバーを克服すればよいと伝えられれば、応募することが可能になるかもしれません。
大切なことは、ペーパードライバーであるにもかかわらず応募しないことです。そのような人材を採用した場合は企業にとってマイナスになるからです。たとえ就業できたとしても、自分が苦しむことになるので嘘はつかないようにしましょう。
まとめ
これから建設設計業界で働きたいと考えている人は、準中型免許の取得や限定解除などを行っておきましょう。業務上、車を運転できることが求められているので、車の免許は取得したものの運転に慣れていない人は運転できるようにしておくことが必要です。運転感覚を取り戻すために練習を重ねれば、仕事でも不安なく車を運転できるようになるでしょう。