測量士とは?地図や建設を支える専門職を紹介
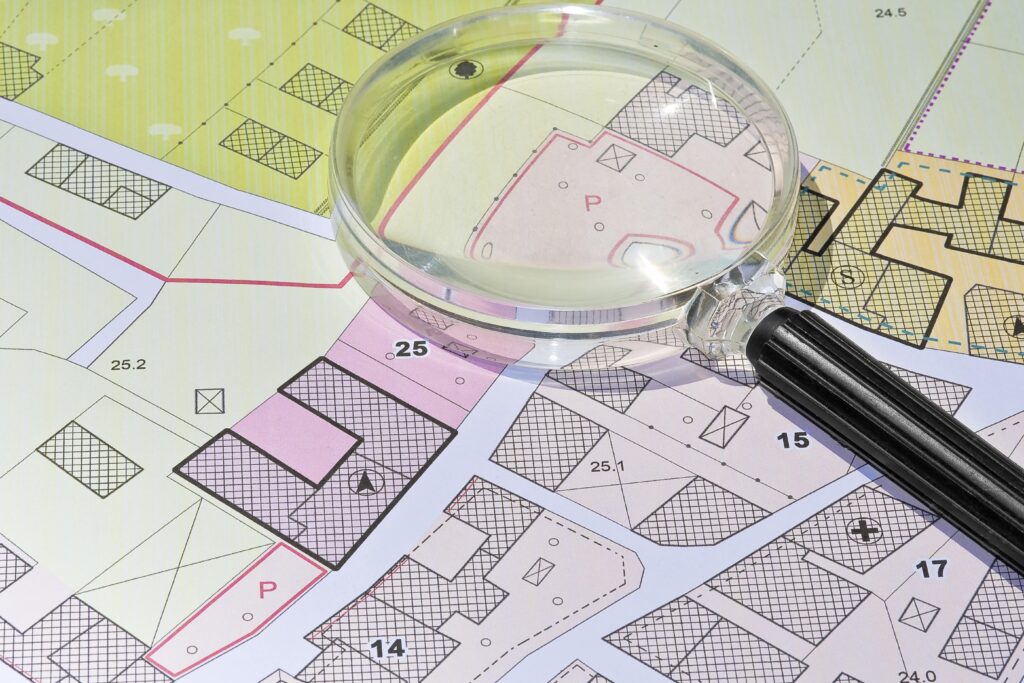
測量士は、建設工事や土地利用の基盤となるデータを測定し、正確な地図や図面を作る専門職です。公共事業から民間の開発まで幅広い分野で活躍でき、社会に欠かせない役割を担っています。そこで本記事では、測量士の仕事内容や資格の取り方、働ける場所や将来性について詳しくご紹介していきます。
測量士とは?建設に欠かせない専門家
測量士は、土地の位置や距離、面積、高さなどを正確に測る専門家です。道路や橋、建物、ダムなどをつくる際には、必ず正確な測量データが必要となるため、社会基盤整備の出発点を担う存在といえます。需要が安定しており、景気に左右されにくい職種のひとつです。
国家資格である測量士は、測量成果に署名や認証を行える唯一の資格者であり、測量業者には事務所ごとに必ず資格者を配置することが法律で義務づけられています。この独占的な地位も大きな特徴です。
実際の業務は大きく分けて、現場で測量機器やGPSを使って計測を行う「外業」と、得られたデータを解析して図面や3Dモデルを作成する「内業」に分かれます。近年ではドローン測量や3Dレーザースキャナーなど最新技術を活用する場面も増えており、従来の精密な手作業に加え、デジタル技術の知識やスキルも求められています。
社会基盤を支える重要な役割を担う仕事であるため、都市開発や災害復旧、防災計画など幅広い分野で活躍の場があります。今後も建設業界のみならず、ITやGIS(地理情報システム)分野とも連携しながら、測量士は欠かせない専門家として求められ続けるでしょう。
測量士になる方法って?
測量士になるためには、国家資格を取得することが必須です。取得方法はいくつかあり、自分に合った道を選ぶことができます。ここでは主な2つの方法を紹介していきます。
学校や養成施設で学んで資格を得る
測量士になる方法のひとつは、文部科学大臣が認定する大学や短期大学、高等専門学校で測量に関する科目を修め、卒業後に実務経験を積むルートです。大学であれば1年以上、短大や高専であれば3年以上の経験が必要です。
また、国土交通大臣が認める養成施設で学び、測量士補の資格を得てから実務経験を積む方法もあります。さらに、測量士補の資格をもっていれば、養成施設で高度な知識や技術を学ぶことで測量士を目指すことも可能です。学歴や状況に合わせて選べるので、計画的に進めることが大切です。
試験に合格して資格を取る
もうひとつの方法は、国土地理院が実施する測量士試験に合格することです。大学や養成施設を経由する方法に比べ、学費や長い実務経験が不要なため、金銭的な負担を抑えられる点が魅力です。
ただし、試験は幅広い知識を問われるため、独学だけでなく専門講座や通信教育を利用して効率的に学ぶ人も少なくありません。学校に通う時間や費用が難しい人にとっては、試験に挑むルートが現実的な選択肢となります。しっかりと準備を整えて合格を目指すことが重要です。
測量士の仕事内容とは?現場からデスクワークまで
測量士は、建設や土木工事を安全かつ正確に進めるために欠かせない存在です。現場での測量からデータの分析まで幅広く業務を担っています。ここでは測量士の仕事内容を具体的に見ていきましょう。
測量計画を立てる役割
測量士の第一の仕事は、建設や土木工事に必要な測量計画を立てることです。工事を進めるには正確な測量が不可欠で、道路やトンネル、ダムなど大規模なプロジェクトもすべて測量から始まります。測量が終わらなければ図面は描けず、工事計画そのものも成立しません。
そのため測量士は、工事全体の出発点を支える専門職といえるでしょう。さらに業務は「測量法」に基づいて行われます。この法律は精度や効率を高めるとともに、制度の改善や業界の健全な発展を目的としたものです。測量士は法の定めに従い、社会に信頼されるデータを提供する役割を担っています。
外業の仕事
外業とは、現場で直接行う測量業務のことです。道路や建設現場で、三脚の機器を覗き込む作業員を見かける機会もあるでしょう。あれが測量士の外業です。従来は「トータルステーション」と呼ばれる機器を使い、距離や角度を計測してきました。
近年は技術の進歩により、ドローンによる空撮測量や自動車に搭載したレーザースキャナでの計測も一般的になっています。
さらに航空写真を活用した測量も広く取り入れられており、現場ごとに適した方法を選択する力が必要です。外業は体力や集中力を求められる仕事ですが、その場で成果を確認できる達成感があり、やりがいを感じやすい分野といえるでしょう。
内業の仕事
もうひとつの業務が「内業」と呼ばれるデスクワークです。外業で収集したデータを整理し、図面化や数値の計算に落とし込むのが主な役割となります。測量計画の立案や予算の管理、機材の準備なども含まれ、業務内容は幅広いのが特徴です。
膨大なデータを扱うため緻密さが求められ、CADソフトや専用プログラムを駆使する場面も増えています。屋外での作業が注目されがちな職業ですが、実際にはこうした内業の比重も大きく、年々重要性を増しています。現場と事務の両方をこなせる柔軟さが、測量士に求められる資質のひとつといえるでしょう。
測量士の年収とやりがい、そして将来の可能性について
測量士は、建設や土木工事を支える専門職として安定した需要があります。収入面も平均より高い傾向があり、やりがいも大きい仕事です。ここでは年収の目安ややりがい、さらに独立の可能性についてご紹介します。
測量士の年収について
測量士の平均年収はおよそ500万円といわれており、日本の平均年収と比べても高めの水準にあります。ただし、これはあくまで目安であり、勤務先の規模や地域、経験年数によって変動します。大手の建設会社や官公庁に勤める場合は収入が安定しやすく、独立して事務所を運営する場合は仕事量によって大きく増減するでしょう。
なお、測量士は国家資格であり、法律で各測量業者に資格者を配置することが義務づけられているため、需要が途切れる心配は少ない職種です。ほかの資格と比べても仕事がなくなる可能性は極めて低く、今後も安定した働き方ができる点が大きな魅力です。
測量士のやりがいについて
測量は単に距離や面積を測る作業ではなく、事前の計画次第で工事全体の効率や精度に大きな差が生まれます。建設現場の土台をつくる重要な役割を担っており、巨大なダムやビルの計画も測量から始まるため、自分の仕事が社会の基盤につながっている実感を得られるでしょう。
また、近年はIT技術の進歩により、GPSや3D測量、ドローンによる空撮など最新機器を活用する機会も増えています。こうした新技術に習熟すれば、ほかの人では対応できない案件を引き受けられるようになり、専門性の高さがそのまま評価につながります。責任は大きいものの、それだけ達成感も強く感じられるのが測量士のやりがいです。
独立開業への道
測量士として経験を積んだ後、さらに土地家屋調査士の資格を取得すれば、独立開業の道が開けます。土地家屋調査士は、土地や建物の登記といった法律業務を行える資格であり、行政書士の資格と組み合わせることで業務の幅がさらに広がります。
測量士の資格をもつ人は、土地家屋調査士試験で一部の科目が免除されるため有利に挑戦できるのです。独立すれば、自らの裁量で仕事を受け、収入面でも大きな可能性が広がるでしょう。将来的に自分の事務所を構えたいと考えている人にとって、測量士は大きな一歩となる資格といえます。
勤務先の違いと転職の考え方
測量士が働く事務所にはいくつかの種類があり、仕事内容も少しずつ異なります。自分に合う環境を見つけることが、長く続けるための大切なポイントです。ここでは勤務先の違いと転職の考え方について紹介します。
公共と民間の違いを知る
測量士が働く事務所は、大きく「公共系」と「民間系」に分けられます。公共系は道路や橋、トンネル、公共施設などの建設に関わる測量が中心です。社会の基盤をつくる重要な役割を担うため、やりがいを感じやすい環境といえるでしょう。
一方で民間系は、住宅地の境界を確定させたり、不動産登記に必要な測量を行ったりするのが主な仕事です。身近な生活に直結する業務が多いため、地域に密着して働けるのが魅力です。それぞれに特徴があるので、自分がどの分野で力を発揮したいのかを見極めることが大切です。
合わないと感じたら転職も選択肢
もし今の職場が自分に合わないと感じるなら、転職を考えるのも自然なことです。測量士は需要が高い資格職であり、さまざまな業界で必要とされています。そのため選択肢は広く、キャリアの方向性に合わせて働く場所を変えることが可能です。
転職活動を始める際には、建築や建設業界に特化した転職サイトを利用すると、自分に合った求人を見つけやすくなります。条件や働き方を比較しながら、長く続けられる環境を探すことが将来の安定につながるでしょう。
まとめ
測量士は、建設や街づくりの土台を支える欠かせない専門職です。資格取得にはいくつかのルートがあり、自分に合った方法で目指すことができます。仕事内容は現場での測量からデータ処理まで幅広く、年収も安定していて将来性の高い職種といえるでしょう。さらに公共系や民間系といった勤務先の違いによって仕事の内容も変わり、キャリアの選択肢も豊富です。もし今の環境が合わないと感じたら転職という道も開かれており、働き方を柔軟に選べる点も魅力です。


































