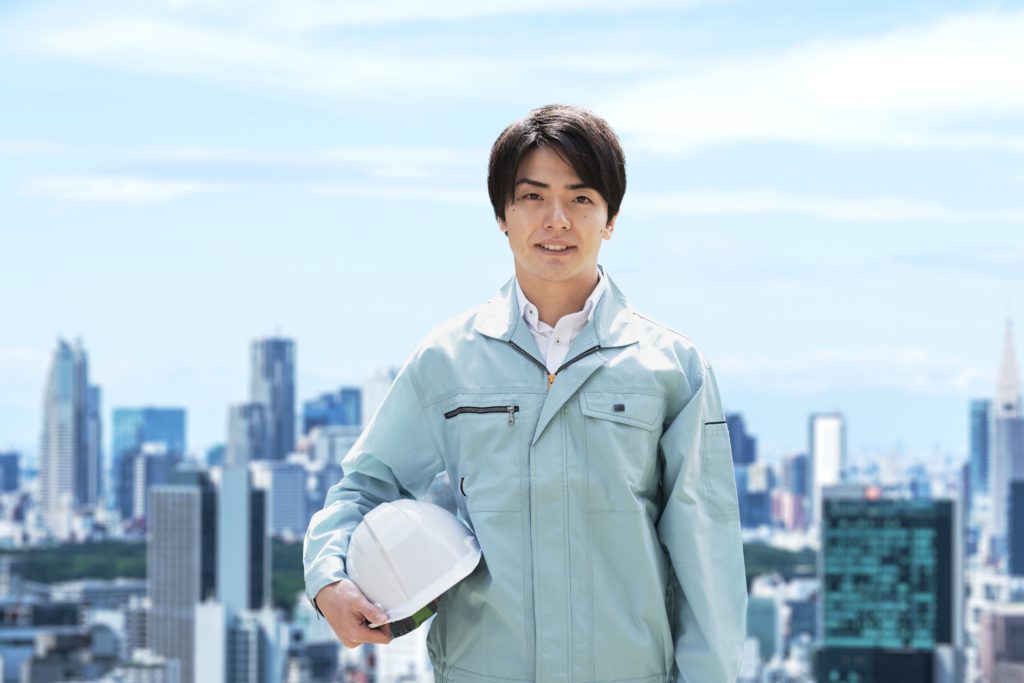一級建築士になるための受験資格は?

建築士とは人々の生活や夢や希望をかなえ、財産を守りながら命や健康を考えて、快適な生活空間を作り出すプロです。建築士に求められる能力や社会的責任はとても大きいですが、その分やりがいのある仕事といえるでしょう。また、建築士は実務経験さえあれば、どんな人でもチャレンジできる資格として注目されています。
誰もが建築士になれるチャンスがある
建物の大規模化や機能設備の複雑化に伴って、建築士の仕事も細分化され、構造設計や設備設計などの専門性がより重視されるようになってきました。しかし、世の中に建築物が存在する限り、建築士は常に必要とされるので、不況下にも強い職業として注目されています。
ところで建築士は国家資格であり、この資格を取得することで、建築に関するプロフェッショナルであるという国のお墨付きをもらえます。同じ国家資格である医師や弁護士は、その資格を持った人でなければできない仕事があります。建築士も同様で、法的に決められた業務があり、資格を持つことで、その仕事を独占的におこなうことができるのです。これを業務独占といいます。
建築士の受験資格には必須の学歴はありません。つまり誰もが建築士になれるというチャンスはあるのです。建築士資格には、一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類があり、どの資格も一定年数以上実務経験があれば、建築や土木に関する専門課程修了といった学歴がなくても、資格試験にチャレンジすることが可能です。例えば一級建築士の受験資格は、二級建築士として4年以上の実務経験があれば良いという決まりがあります。
そして、その二級建築士になるためには、7年以上の実務経験を積んだ人であれば、その受験資格を得ることができます。建築士の受験資格は、建築士法と呼ばれる法律によって、学歴と建築に関する実務経験年数の両面から規定されています。そのため、現在の自分の状況によって、建築士になるためのルートを作ることが肝心です。
建築士は、数ある建築関連資格の中でも最高峰に資格だといわれています。決して易しい試験ではなく超難関資格といわれていますが、それだけに資格取得後の社会的ステータスは格段に高くなるというメリットがあります。
企業の終身雇用制や国の年金制度が、確実に生活を保証してくれるとは限らなくなった時代の中で、このような国家資格取得は個人の大きな武器となる時代です。つまり、国家資格である建築士資格を取得することは、安心と情勢の変化への備えになることは間違いありません。
建築士の種類及び試験の流れについて
先述したように建築士資格には、一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類があります。そのため、級の違いや名称の違いについて関心を持つ人は多いです。一定規模以上の建築物の設計や工事監理は、建築士の資格を持つ技術者でないとおこなうことはできません。
ちなみに工事監理とは、建築主の立場に立って、工事が設計図書の通りに実施されているかどうかを建築士が確認することを指します。建築士法では「一級建築士」・「一級建築士或いは二級建築士」・「一級建築士、二級建築士或いは木造建築士」がおこなえる設計・工事監理を、対象の建物の規模や構造や用途別ごとに定義して、それぞれを区別しています。
これは、応急仮設建築物や都道府県の条例による例外を除いて、建築物の増改築や大規模な修繕やリフォームなど、全ての場合において適用されています。資格の区別において扱える建築物の規模は異なりますが、業務内容や作業の流れについては、どの建築士資格であっても基本的には同じです。
ところで建築士試験は年に1回実施され、学科試験と設計製図試験と2種類が課せられます。学科試験に合格した人だけが、次の設計製図試験に進める形式です。試験の時期は例年7月から10月にかけて、約2か月半かけておこなわれます。一級建築士・木造建築士と、二級建築士では試験の日程が少しずらされています。
そのため、二級建築士試験とそれ以外の2つの建築士試験のうち、どちらかとを組み合わせてW受験することが可能です。一級建築士試験の試験は学科試験・設計製図試験とも、全国一律で実施されます。また二級建築士と木造建築士の試験は、全国を8つのブロックに分けておこなわれます。
学科試験は全国一律ですが、設計製図試験は各ブロックで異なることがあります。受験は住所地の都道府県でするようになっていて、受験申し込み後に試験地を変更することはできないため注意しなければなりません。申し込みから試験までの流れとしては、まず4月頃から各都道府県の建築士会や行政機関の建築担当部署などに、試験申込用紙が配布されます。配布期間は約10日ですが、そのうちの後半5日間が受験申込期間です。このように、受験申込期間は決して長くないことは知っておきましょう。
また、申込用紙を取りに行けない人に対して、インターネットによる受験申込があります。書類審査による受験資格が確認された後に、7月上旬から二級建築士の学科試験がスタートします。それ以外の建築士の学科試験は7月下旬からスタートします。学科試験合格発表後、9月と10月にそれぞれの設計製図試験がおこなわれます。そして最終的な合格者発表は例年12月頃となっています。
受験資格の詳細をチェックしよう
建築士試験は誰でもチャレンジできる国家資格ですが、それぞれに受験資格が定められています。基本的には学歴と実務経験との組み合わせですが、いろいろなケースがあるため、まずは現在の自分がどこに該当するのかを確認することからスタートします。そして、要件を満たすためには何が必要かをしっかりチェックしましょう。
まず一級建築士を受験する場合、二級建築士と建築設備士の資格があって4年以上の実務経験があれば、学歴に関係なく受験資格が得られます。もし二級建築士と建築設備士の資格がない場合、学歴の内容によって受験用件の実務経験年数が変わってくるので注意が必要です。例えば同じ建築土木の課程であっても、4年制大学卒業者は実務経験2年以上であるのに対して、3年制短期大学卒業者は実務経験3年以上となります。
さらに3年制短期大学や高等専門学校卒業者では4年以上の実務経験が課せられます。一方、二級建築士と木造建築士の受験資格は同じであり、受験資格に年齢制限はありません(ただし未成年者は除く)。さらに建築に関する学歴がなくても、7年以上建築に関する実務経験を積んでいれば試験を受けることは可能です。
また、二級建築士と木造建築士は学歴のみで試験を受けられるケースがあります。都道府県知事が、教育内容を踏まえ認定した学校を卒業した場合がそれに該当します。これには建築系の大学のほか、専修学校などが挙げられます。
このように建築士の試験は、受験できる資格として認められる学歴さえあれば、試験に必要とされる実務経験年数は短くて済むという特徴があります。もし建築士を目指してこれからの進学先を選ぶのであれば、学校のカリキュラムによって、卒業後の実務経験は変わってくるため、学校選びはしっかり検討する必要があるのです。
建築士にはいくつかの級がありますが、学歴と実務経験の組み合わせで受験できるか否かが変わってきます。学歴によって実務経験年数が変わってくるので、しっかり考えて進学先を決めなければなりません。しかし、誰にでも建築士になれるチャンスはあることは是非知っておくと良いです。
また、どの建築士試験も受験期間は2~3ヶ月程度とかなり長丁場です。しかも年に1回しかチャンスがないので、スケジュールを立ててしっかり試験対策する必要があります。無事に合格できれば社会的ステータスは上がるので、建築業界を目指すなら是非チャレンジしたい資格です。